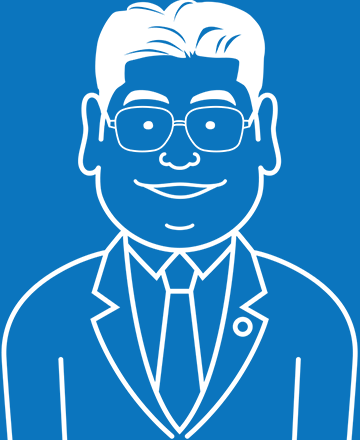結局のところ、相続対策に何をすればいいの?
結局、相続対策には何をしたらいいの??
統計によれば、65歳以上の高齢者はの認知症は、いまや6人に1人。
2022年の統計で65才以上の人口は約3627万人ですから、単純計算で約600万人以上が該当します。
そんな中で、どのように終活・相続対策をしていくべきでしょうか?
後見制度、任意後見、家族信託、遺言・・・いろいろな方法があって、どれを使ったらいいのか判断に迷われるかと思います。
今回は、この辺りを考えていきたいと思います。
後見制度の闇、家族信託の闇。解決策は・・・。
判断能力が不十分な、潜在的な認知症群の方を含むと、1000万人。
それに対して、この認知症の方をサポートする成年後見制度の利用者数が、
2021年で、24万人にとどまるという統計があることをご存じでしょうか?
なぜ、利用が進まないのでしょうか?
大きな要因の一つは、成年後見人を、本人・ご家族の意向で選ぶことができないからと言われています。
本来であれば、本人・ご家族の意向を尊重して、その指名される方を選任するのが、本人意思の尊重にもなるかとは思います。
しかし、親族間の対立、選任候補者としての適格、不正防止の必要性、本人のニーズの程度などを総合的に見ていく必要があります。
だから、本人・ご家族の意向をそのまま尊重するわけにもいかない。
そこで、成年後見人の選任は家庭裁判所の専権事項とされています。
たとえ申立にあたって推薦したとしても、あくまで「参考意見」にすぎません。
ところがこれがかえって成年後見人制度の利用がすすまない要因にもなっているのです。
成年後見利用促進法の関係で設置された中核機関がうまく作用して後見人推薦機能を十分に果たせれば、この点は改善されるかもしれません。
しかし、現時点では、家庭裁判所は親族後見人に適任者がいれば親族後見人を選びますが、親族に後見人候補者がいない、財産が多い、親族間に紛争があるなど一定の場合には、ほぼ専門職後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士)を選任します。
そのために起こる、本人・ご家族との意向のずれ。
本人・ご家族にとっては、全く知らない専門職後見人が選任されることになります。
ある日突然、親族の中に全くの第三者が割り込んできて、比喩的に言えば「財布の中に手を突っ込んでくる」わけです。
当然いろいろな葛藤が生じますよね。
さらに、専門職後見人は業務として後見人をするので、必ず報酬が発生します(親族でも法律上は報酬は発生しますが、報酬を求めないこともよくあります。)。
収入・財産が十分あればいいですが、それほどない場合にはどうやって後見人報酬を捻出するか。報酬を捻出できなければ専門職後見人はつけられません。
他方で、財産がたくさんあっても、後に相続財産として受け取ることを期待して、後見人報酬として支払うことを拒否したい親族の意向とも真っ向からぶつかります。
だから、成年後見人の利用が進まないと面があるのでしょう。
家族信託についてはどうなのか?
そこで、成年後見制度の利用を回避するため、家族信託が次の手として考えられます。近時のトレンドでもあります。
家族信託では、本人・ご家族が、受託者を選任することができます。
信託契約の定め方次第で柔軟な運用も可能です。
後見人制度のような、見ず知らずの人が、本人の財産管理をするというようなことは想定されません。報酬も信託契約の中で定められるので、予想の範囲内にとどまります。
ところが、この家族信託は、柔軟性の裏返しとして、受託者への監督機能が乏しいのです。
専門家によるチェックを受けることができない。
専門職がチェックできるのは、設定だけ、スタートの時点だけです。
公正証書の作成だけ。
ところが、そのあとの、内容通りの執行ができているかを、監督する機関はないのです。
信託契約の中で設定することもできますが、家庭裁判所のように公的機関が監督するものではありません。
もしも専門職に監督を委ねれば、監督費用が発生するので成年後見制度をわざわざ回避する意味が減少してしまうでしょう。
言えばきりがないですが、信託監督人を監督する機関がないので、本当に適切に監督されているか、信託の受託者となれ合いになっていないかチェックできません。
ある意味性善説に立たざるを得ない制度です。
そのため、トラブルが起きていても誰も気づかない。
横領もわからないという状況になってしまいかねないリスクがあります。
裁判所の監督を回避することを目的とした柔軟な制度設計ゆえに、デメリットも存在するのです。
では、任意後見はどうなのか?
そこで、本人・ご家族の意向も尊重しつつ、専門機関によるチェックを受ける運用がベターではないでしょうか。
そこで、おすすめなのが任意後見制度です。
任意後見であれば、見ず知らずの他人ではなく、家族や知人を任意後見人に選任することができます。
そして、任意後見人の監督として、専門家も選任することができます。
それも、以前から知っている専門家を、です。
それでも任意後見が進まない理由は、お金にあると言われています。
任意後見がスタートすれば、家庭裁判所から任意後見監督人として専門職後見人が選任されます。この任意後見監督人には、専門職なので報酬が発生します。
そのため、任意後見人+任意後見監督人の2名分の報酬がかかってしまうのです。
もちろん、任意後見人の報酬はなしと定めることもできますが、少なくとも任意後見監督人1人分の報酬は発生しますので、「せっかく報酬を節約するために成年後見人ではなく任意後見を利用したのに!」という当初の思惑と違った運用になってしまうこともあります。
ただ、監督人にかかる報酬を適切に業務が行われるコストと考えれば、それが高いと感じるかどうかは人それぞれです。
亡くなってからの対策として、遺言を
とはいえいろいろな制度の良いところ取りをしている任意後見契約です。
任意後見契約と併せて、亡くなってからの対策を、遺言書を書いておくことで備えることが重要です。
なぜか。
任意後見人及び任意後見監督人の業務は、本人が死亡した瞬間に終了します。あとは引継ぎの残務処理を残すだけです。
死亡後に財産をどうするかは、遺言によって決めておく必要があります。
あわせて、遺言事項以外の諸々のことを誰かに頼んでおくには、死後受任契約も公正証書にしておくこともできます。
やはり、本人の意思を尊重するという観点からは遺言をベースに進めていくことが一番でしょう。
イメージとしては、遺言が最低限で、そこに死後事務委任契約を足すことで死後のことを包括的に依頼します。加えて、認知症になったときに備えて任意後見契約を締結しておき、さらに認知症になる前に前倒しするには財産管理契約を、という形で対策を採ります。これらをあわせて「4点セット」ということもあります。
遺言書の書き方は専門家へご相談を
遺言には多くの種類があり、遺言の種類によって厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、不備があるために無効になることもあるのです。
当事務所では、遺言作成に必要なアドバイス、必要な書類の準備などの全体的なサポートを行っています。
ぜひご相談ください。