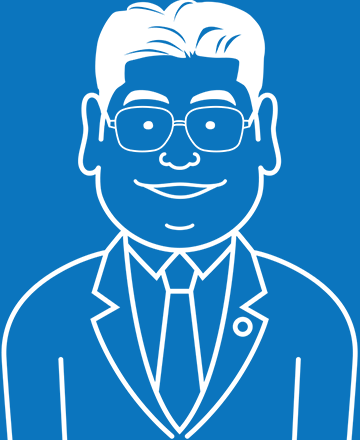- 財産管理契約
- 任意後見契約
- 遺 言
- 死後事務委任契約
高齢者の法律相談Elderly Life
終活は何をしたらいいか
Life Planning

片山法律事務所
弁護士 片山 智宏
安心できる老後を送るために。
我が国は超高齢化社会を迎え、とりわけ山口県では高齢化率が全国的に見ても高い水準です。
高齢者をめぐる法律問題の特色は、短期間に複数の問題が絡み合って発生してくるところにあります。
だからこそ、事前に問題が大きくならないように、対処しておく必要が高いのです。
高齢者を巡る問題は、
①平穏な老後をどう送るか
②遺族に財産をどう残すか(相続)
に大別することができます。
平穏な老後を送るための障害となるのは、2つです。1つは身体的な不都合で、介護の問題です。もう1つは、判断力が衰えた場合に、財産を適正に管理できなくなることで、誰かが本人になりかわって財産を管理する必要があります(財産管理)。悪質な業者が高齢者の家に入り込み、高額な金融商品や不必要な羽毛布団を大量に買わせるといった事件のニュースを覚えていらっしゃる方も多いでしょう。このようなときに、誰かが財産を管理していれば、被害を防ぐことができたかもしれません。
終活で起こる問題を回避するために
上記は合わせて4点セットと言うことがあり、この4つの契約を合わせて公証人役場にて公正証書で作成することが、終活として行うべき点になってくるのです。
ホームロイヤーのオススメ
①財産管理契約 ②任意後見契約 ③遺言 ④死後事務委任契約 の4点セットにご本人の意思を反映させるには、継続的にお客様のご要望を聴き取り、人生観、価値観といった内心のことから、お墓がどこにあるか、その宗教は何か、ご葬儀はどの程度の規模で行いたいかといった祭祀のこと、財産がどこにどれくらいあるかといった財産面のことなど、挙げればきりがないほど多くのことを正確に把握しなければなりません。
そのためには、弁護士が1時間程度1、2回面会すれば足りるようなものではなく、数ヶ月から数年にかけての長期間の関与が必要です。
また、4点セットで弁護士が受任者となれば、それこそ依頼者が死亡した後まで関与し続けることになります。こうした長期間の関与を前提として一種の顧問契約(ホームロイヤー契約)があります。
ホームロイヤー契約では、原則として1か月に1回程度、電話又は直接お会いして、状況を確認することが基本となります。
その際に、法的紛争に巻き込まれていないか、次の法的手段にすすむ段階にきていないかなどを注意し、必要に応じて福祉サービスと連絡を取るなどをします(見守り)。
財産管理契約
今までの日本社会では、多くの場合高齢者の子どもが介護の一環として親の財産を管理することが多かったといえます。親族が管理する利点は、報酬がかかりませんし、身内ならではの気安さがあります。しかしながら、身内だからこそ言えないことがありますし、最近では「自分は義理の父母の介護で大変苦労したので、子どもに苦労をかけたくない。」という声も多く聞かれるようになりました。
身体的介護は介護サービスを利用するように、財産管理の場面でも専門家のサービスを利用してみてはいかがでしょうか。
これは、民法上の委任(準委任)契約です。契約により、財産管理権を第三者に委ねるものです。契約ですので、どの範囲の財産を(全部か、一部か)どのように管理してほしいのか契約者の意思を反映させるための融通がききます。他方、契約ですので判断力が低下してからでは使えませんし、公的制度でないため受任者の地位が不安定で、いざというときに必要な法的手段をとることができないリスクがあります。このようなリスクを回避するため、他に任意後見契約や成年後見と組み合わせ、適宜これらに移行していく必要があります。
成年後見制度
すでに判断能力が低下してしまった場合には、家庭裁判所に対し、成年後見人の選任を申し立てることになります。個々人の判断能力の低下には程度に差がありますので、低下の程度により、保佐や補助といった制度になります。
成年後見人は、裁判所が選任した上、その監督までするため、成年後見人の法的立場が安定し、業務遂行に対する監督が行き届きやすいという利点があります。また、すでに判断能力が低下してしまった場合には、成年後見をはじめとする法定後見制度を使うほかありません。
しかしながら、裁判所という公的機関が業務遂行を監督する以上、後見人には財産を管理するにあたり裁量の余地があまりなく、必要最低限の収入と支出の管理(例えば、年金を受領して病院への支払いをするなど。)のみを行い、元本割れするリスクのある運用などはできません。被後見人が望む支出であっても、後見人と裁判所が協議した結果、支出が認められないことも多々あります。ご家族が「(被後見人が)元気な時はこうしてくれといっていたので、お金を出してほしい。」というご要望を出されることもよくありますが、成年後見人と裁判所の判断でご要望にお応えできず、険悪な雰囲気になることもしばしばです。
成年後見が必要となるのは、判断力が低下した高齢者ご自身というよりも、家族や親族等、周囲の人々の方かも知れません。成年後見が必要になるほど判断力が低下すると、例えばご兄弟で相続があった場合に遺産分割ができず宙に浮いてしまう場合があります。その際に、成年後見人を選任したうえで、遺産分割協議をすることになります。
任意後見契約
公証人役場で公正証書を作成することで任意後見人を選任します。本人の判断力が低下した段階で、申立により裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見が開始されます。任意後見人は、任意後見監督人の監督の下で、後見事務を遂行します。
公正証書を作成する必要がある点で財産管理契約よりも煩雑ですが、専門家である公証人が作成するので不合理な契約の内容にはなりませんし、任意後見監督人の監督があるため不正が行われにくくなっています。また、公正証書を作成する段階で決めておけば、任意後見人の業務遂行にあたってかなり自由にご本人の意思を実現させることができます。
財産管理契約と成年後見契約の良いところ取りをしたような制度ですので、もっと活用を図るべきでしょう。
任意後見契約は、判断力が低下してから発動する制度ですので、判断能力が十分なうちから財産管理を委ねたいという場合には、財産管理契約と併用する必要があります。また、契約である以上、すでに判断力が低下してしまった場合には任意後見契約をすることができません。
遺 言
死後に財産を誰にどのように残すかは、重大な関心事でしょう。遺言がないまま相続が発生すれば、原則として法定相続分に従った機械的な分割がなされますので、現実にそぐわない不公平な結果を招くことがあります。残された遺族が年々もかけて争うため、「争続」などといわれることもあります。弁護士から見ると、「遺言があればここまで揉めなかったのに。」という事案は多くあります。
遺言をする際の注意点は、 相続 の項目をご覧下さい。
実際に遺言をされる場合には、専門家の意見を求めてからにすることを強くおすすめします。
死後事務委任契約
任意後見人及び成年後見人(保佐人・補助人を含む。)の職務は、本人(委任者)の死亡により終了します。あとは、管理する財産を相続人に引き継ぐ業務が残るだけです。例えば、死亡時に入院していた病院や施設の支払などは、厳密に言えば成年後見人が支払うことはできません。死亡と同時に相続人に債務が相続され、相続人が支払うのが法の建前です。それでは病院や施設に迷惑をかけてしまうので、成年後見人が各相続人の意思に反しない範囲で成年後見業務に付随する業務として支払うことはありますが、法の建前からすれば危ない橋を渡っていると言わざるを得ません。相続人が激しく争っている場合には、病院や施設の支払が宙に浮いたままいたずらに時間だけが過ぎる場合もありえます。病院や施設側とすれば、いつ支払われるか分からない人を危なくて入所を躊躇せざるをえない場合もあるかもしれません。
他方、相続人にどのように財産を引き継ぐかは、遺言によって決めておくことができます。ただし、遺言によって法的効果を有する事項は、法律によって定められています(法定遺言事項)。これは、自分で作成した遺言(自筆証書遺言)であろうと、公証人が作成した遺言(公正証書遺言)であろうと変わりません。もちろん、遺言には付言という形で法定遺言事項以外のことも記載できますが、法的な効力は持ちませんので単なる故人の願望にすぎず、それが実行されるかどうかは残された人々次第です。
そこで、任意後見及び成年後見と遺言の間隙を埋めるものとして、死後事務委任契約が必要になります。
このように、 ①財産管理契約 ②任意後見契約 ③遺言 ④死後事務委任契 を合わせてまとめておくことより、元気なうちから死亡後まで隙間なく自己の意思を実現していくことができるようになります。
この4つのものを併せて同時に公正証書を作成することが望ましいでしょう。財産管理契約、任意後見契約及び遺言をまとめて三点セットと呼び、これに死後事務委任契約を加えたものを4点セットと呼ぶことがあります。
事業承継
会社経営者の方が、どのように円滑に会社経営から身を引き、次の経営者に引き継ぐかという問題です。世に事業承継の情報はあふれていますが、比較的大きめの会社を想定したものが多く、中小・零細企業を対象とする場合には、そのまま使えない枠組みもあります。
事業承継には多数の問題がありますが、突き詰めて言えば ①株式の承継 ②会社財産の承継 ③取引先の引継ぎ ④税金 に大別できます。
事業承継は、④税金の問題が先行して、いかに税金を低くするかに意識が向きがちです。税金の場合には税理士が専門であることはいうまでもありません。
しかしながら、税金を安くすることばかりに気をとられ、株式を適切に承継させなかったために、相続で争いになるような事態は本末転倒です。取引先の信頼も失い、倒産ということになりかねません。 ①株式の承継 及び ②会社財産の承継 は遺言や生前贈与を利用し、さらに会社法上の制度(種類株式の発行等)も組み合わせて「争続」や会社支配権を巡る紛争が起きないように、御社向けにカスタマイズした方策をとることが必要です。これは弁護士が得意とする分野です。
経営者の方は、会社には顧問弁護士がいるので、顧問弁護士に相談すればよいとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、顧問弁護士は会社に対して忠実義務を負っているので、会社と経営者の利益が相反する場合、会社の利益を優先させなければなりません。経営者が自己の利益を守るためには、顧問弁護士とは別の弁護士に依頼する必要があります。
当事務所では、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等支援機関の認定を受けており、事業承継の問題にも対応しています。また、協力関係にある税理士と協働して税金にも配慮して業務遂行することが可能ですので、ぜひご相談ください。

施設管理者・ケアマネ様へCONSULTING LAWYER
ご入所/入居をお考えの利用者様に、ご家族がいらっしゃらない・認知の疑いがあるといった場合、入居後のケアプラン作成に不安な点が多々生じることと思われます。
事前に弁護士と相談されることで、上記のような予防策を立て、安心したケアプランの作成を実現することが出来るようになります。
一度、ご相談されてみませんか?
相続についての問題
Inheritance
相続争いは誰の身にも降りかかる可能性があります。
相続は、逆縁という悲しい事態が起こらない限り、誰でも一生のうちに数回は遭遇する現象です。
相続は、文字通り血を分けた親族間での争いとなります。財産という経済的利益と積年の感情的な対立が複雑に絡み合い、噴出します。歴史を紐解けば、古今東西、跡目争い(相続)を巡って大きな戦争が何度も起きており、多くの人が命を失っています。小説でも題材となることが多く、横溝正史原作の「犬神家の一族」も相続にからんだ殺人事件といえます。
「争いになるのはお金持ちだけで、うちは財産なんてないから争いになるはずがない。」と軽く見るのは早計です。財産が多ければ土地を長男に、同価値の預金を二男に、と分割することができます。財産が少なければ、同価値の預金を用意することができず、どう分けるかが激しく争いになるからです。自宅土地建物しか財産がないという場合は、最も激しく争われる類型の一つです。
感情をお互いにぶつけ合っても問題は決して解決しません。法律という客観的なルールをふまえて、それを補うために相互に譲り合いウィン・ウィンの関係を目指さなければなりません。そのためには、当事者の激しい感情から一歩引いて冷静に考えることができる弁護士を代理人として遺産分割にあたることが極めて効果的です。
手 続
相続人の間で話し合った結果、話し合いがまとまれば一番良いのは、離婚と同じです。円満な親族関係が維持され、今後とも助け合って生きていくことができるのでしょう。この場合であっても、不動産の名義変更や銀行での手続のために遺産分割協議書を作成しておくことが望ましいでしょう。
遺産分割協議は、えてしてまとまらず、話し合いをすればするほど相続人の感情的対立が激しくなることがあります。刀傷沙汰になることもあります。近しい親族だからこその積年の思いが積もっていますし、相続人の配偶者や知人が横槍を入れて対立を煽る場合も多いです。
遺産分割協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。裁判所の力を借りて話し合いをすることになります。調停の場合には、調停委員を通して主張し合うことができ、直接顔を合わせないようにすることもできますので、多少は冷静になって話し合いを進めることができます。
調停による話し合いでもまとまらなかった場合、審判という形で裁判所が一刀両断に結論を出して紛争を解決に導きます。一刀両断ですので、個別のこの財産はほしいというような調停で希望していた事柄が実現される保証は全くありません。不満であれば抗告し、高等裁判所の判断を仰ぐことになります。
相続対策(相続発生前にしておくこと)
- 遺 言
相続で紛争が激しくなる最大の根拠は、紛争が起きたときに、その紛争の原因に最も関与した当の本人は亡くなっており、話を聞くことができないことです。まだ相続が発生していないのでしたら、まずは争いにならないよう遺言をしておくことが極めて有効です。
遺言には、大きく分けて自分で書く自筆証書遺言と、公証人に作成してもらう公正証書遺言があります。自筆証書遺言では紛失の危険などもありますので、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしています。ご依頼があれば、弁護士が遺言作成者のご意向の聴き取りを行い、公証役場と文面の調整をした上、公正証書遺言の立会人となり、公正証書の正本をお預かりする業務を行っています。 - 税金対策ばかりに目が行かないように
遺言は相続対策の重要な手段ですが、誤った内容の遺言をしてしまうと、余計に紛争をまきおこしかねません。一番注意しなければならないのは、遺留分(民法1028条以下)を侵害しないような内容にすることです。
遺留分とは、分かりやすく言えば、被相続人の子は、遺言によりそれよりも少ない遺産しかもらえなかったとしても、法定相続分の2分の1の割合の財産については、多く受け取った相続人に請求できるというものです。せっかく遺言をしても、遺留分をめぐる争いを誘発してしまっては元の木阿弥です。
また、相続対策というと税金対策にばかり目がいきがちですが、それがかえって争いを激化させることがあります。例えば、税金対策で遊休土地に銀行から借り入れをして賃貸アパートを建てることがあります。相続税の面から言えば、確かに節税効果があるのでしょう。しかし、遺産分割という面から見れば、一番分けやすいのは預貯金です。賃貸アパートは売ってお金に換えなければ分割できません。一方が売却を求め、もう一方が売却に反対するような場合には、遺産分割が完了するまで売却することはできません。仮に、売却することに合意を得られたとしても、少し不動産市況がよくなったとはいえ、すぐに買い手を見つけることは難しいでしょう。急いで売却する場合には足下を見られて価格は下がるでしょう。相続税の申告期限は死亡日の翌実から10か月以内ですので、万が一賃貸アパートが売れなかった場合、遺産分割ができないので申告ができず、無申告加算税が発生しかねません。
他に、例えば、親が孫かわいさに孫名義の預金をしているようなことがあります。その孫の親である相続人は孫が贈与を受けたものだと主張し、他の相続人は遺産なので分割せよと主張するに決まっています。こうして、孫かわいさの善意がかえって火に油を注ぐことになるのです。
遺産分割~相続発生後にすること
- 3つの関門
遺産分割で考えるべきことは、①相続人は誰か、②遺産に含まれる財産は何か(その財産をいくらと評価するかを含む。)、③遺産をどう分けるか、です。これらをすべて遺漏なく決められるならば、専門家が介入することなく、相続人だけで遺産分割協議をまとめることができます。しかしながら、以下に見るように、それぞれ難しい問題がありますので、専門家を交えず相続人だけで完結することは難しいでしょう。
- 相続人の確定
誰が相続人かは、一見明白なようにも思われます。例えば、父(既に死亡)、母、独立した子3人(長男、二男、長女)の家族で母が死亡したため遺産分割が必要となった場合を考えます。3人の子からすれば、自分たち以外に相続人はいないことが明白と考えているかも知れません。ところが、母には離婚歴があり、前夫との間に子が一人いて、そのことを夫にも自分の3人の子にも恥ずかしくて伝えられないまま、文字通り墓場までその事実を持って行ったような場合、前夫との子も相続人になります。
また、とりわけ戦前の家制度が強かった時代には、養子縁組がなされることも多かったようで、思いもかけない養子が存在するかも知れません。
したがって、他に相続人はいないと思う場合でも、必ず被相続人が生まれてから死ぬまでの戸籍を調べなければなりません。判例上、相続人を漏らしてなされた遺産分割協議は無効です。 - 遺産に含まれる財産は何か
理論的に言えば、被相続人死亡時に被相続人に帰属していた財産すべてです。
被相続人名義のすべての財産であることが明らかであるように思われますが、そうとは限りません。他人名義の預金であっても、お金の出所や届出印の保管状況によっては遺産になりますし、逆に被相続人名義の預金であっても遺産ではないこともありえます。ただし、他人名義の財産が遺産であることを主張する場合には、遺産分割とは別の裁判で立証しなければなりません。税金対策に気をとられるあまり、余計に紛争の火種を残すことは避けるべきでしょう。
注意しなければならないのは、遺産分割は、今ある財産を分割するにすぎないということです。よく、「昔、○○という財産があった。今もどこかにあるはずなので、それも遺産である。」という主張がなされることがあります。遺産分割では解決することのできない問題です。相続人の間の合意が得られない場合、法律の制度上、別の裁判を起こして立証しなければなりません。裁判ということは、自分に有利な証拠は自分で探さなければなりません。今見つからないから問題にしているのであって、それがどこかにあるはずだという立証は困難を極めます。訴訟提起を断念せざるを得ないことも多いでしょう。
遺産を金額的にいくらと評価するかも争いになることがあります。
不動産は「1物4価」といわれるとおり、時価(実勢価格)・公示価格・路線価・固定資産評価のいずれによるかにより、金額に差が出てきます。
また、美術品・工芸品などは、購入時には何百万円もした場合でも、いくらも値段がつかない場合もあります。
こうした財産の一つ一つの金額を何を基準に判断するかを決めていく必要があり、案外この点が争いになることがあります。 - 分割方法
今日では、民法の定める法定相続分をベースにして、微調整を加えて分割するという大枠は合意できることがほとんどです。
しかしながら、具体的にどう分割するかは激しい争いになります。各相続人には、個別の財産に対する思い入れ強弱があります。例えば、長男は自宅土地建物は先祖代々受け継いできたものだから何があっても自分が守り抜くといい、二男は自宅土地建物を売ってお金に換えて2分の1ずつ分けろというかも知れません。
弁護士的に言えば、遺産はすべて預貯金にしておいてくれたほうが助かります。預貯金であればどうにでも分割できます。
分割方法は、知恵を出し合い、譲るべきは譲り合い、できる限り相続人の希望に添う形で決めていくことが肝要です。
法定相続分の修正特別受益・寄与分
- 特別受益
共同相続人中に、被相続人から、①遺贈、②婚姻・養子縁組のため生計の資本として贈与を受けた者がいるときは、贈与額を予め相続財産を受け取ったものとみて、持ち戻し計算をします(民法903条)。特別受益がなかったならば被相続人が有していたはずの財産を遺産と考えるのです。生前贈与ならば何でも特別受益になるわけではなく、①又は②の目的での贈与に限られます。
遺産分割調停になった場合、特別受益の主張がなされることがよくあります。例えば、兄弟3人が父親の遺産を相続する場合、「長男は結婚したときに家を建ててもらった。」、「二男は会社を設立する際に営業資金を援助してもらった。」、「三男だけは私立大学の医学部に行かせてもらった。」という具合に、過去の積年の感情が噴出してくるのが特別受益の場面です。
特別受益を主張することは、慎重に判断する必要があります。相続発生の何十年も前の事柄であることが多く、証拠が散逸していることがほとんどで「もらった。」「もらってない。」という争いになった場合、立証のしようがありません。
また、一人が他の相続人の特別受益を主張し始めると、十中八九、他の相続人も別の特別受益を主張し始めて収拾がつかない事態になりかねないからです。そうなると、調停などの話し合いで決着をつけることは絶望的なります。
その挙げ句、特別受益がある場合には、持ち戻し計算をした金額が遺産の評価額となりますので、相続税の対象が増える結果、相続税が増えてしまう可能性があります。ですので、民法上特別受益という制度があるからといって、その主張をするか否かは思案のしどころです。 - 寄与分
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、相当額を予め遺産から控除し、寄与をした者の相続分に上乗せするという制度です(民法904条の2)。
寄与分が認められる類型としては、被相続人の家業を手伝う(家業従事型)、被相続人に資金援助をしていた(金銭出資型)、体調を崩した被相続人の面倒を長年みてきた(療養看護型)、などが典型例です。
寄与分は共同相続人の協議により定めますが、協議が整わないときは、家庭裁判所が一切の事情を考慮して定めます(同条2項)。とはいえ、通常親族であれば助け合う意思と義務がありますので、何らかの貢献をしたというものでは全く足りず、それを超えた特別の寄与が必要です。そう簡単に認められるものではありません。
寄与分の主張も、遺産分割を紛糾させる原因となります。「自分は(長男)、親の身の回りの世話を押しつけられてきた。」、「自分は(二男)、父の家業が苦しいときに資金援助した。」という具合に、特別受益と同様に積年の思いが噴出してきます。結局、寄与分が決まらなければ遺産分割できないので、紛争を長引かせる要因になってきます。早期に決着させたい場合には、不満はあっても寄与分の主張をあえてしない、その代わり多少自分が取得する財産に色をつけてほしい、という主張に切り替えていくべき場面もでてくるでしょう。
相続放棄
- 相続放棄とは何か
被相続人が借金ばかりを残して死亡した場合、相続人としては相続放棄をすることになるでしょう(民法938条以下)。
相続放棄により、はじめから相続人とならなかったこととみなされますので(民法939条)、配偶者と子が全員放棄した場合、相続人の親(尊属)や兄弟が債務を相続する可能性が出てきます。親族に与える影響が大きいので、専門家にご相談されることをお勧めします。 - 相続放棄の手続
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述という法律上の手続をとらなければなりません。
勝手に、他の相続人に対して「放棄するから後はよろしく。」というだけでは足りません。
3か月を経過してしまえば、相続を承認したことになり、もはや放棄をすることができなくなります。
注意しなければならないのは、放棄する以前に一定の行為をした人は、放棄をすることができなくなることです(法定単純承認、民法921条)。 - 3か月を経過してしまった場合
相続人の死亡後3か月以上を経過してから相続人に借金があったことを知った場合には、判例上、それを知った時から3か月以内に相続放棄をすればよいとされています。これは、音信不通であった父が死んだことは風の便りで聞いていたが、それから何年もしてから父が消費者金融から借金をしており、その消費者金融から督促状が来た、というケースでは、督促状がきてから3か月以内であれば相続放棄できるということです。
死亡後3か月以上経過してしまったので放棄できないと諦めることなく、専門家に相談されることをおすすめします。
ご相談や費用に関するお問合わせはお気軽にご連絡ください。
片山法律事務所では様々な疑問や質問に丁寧に対応いたします。
まずは電話かメールでご相談の予約をお願いします。
また、費用に関するお問合わせ等、どんなことでもお気軽にご連絡ください。