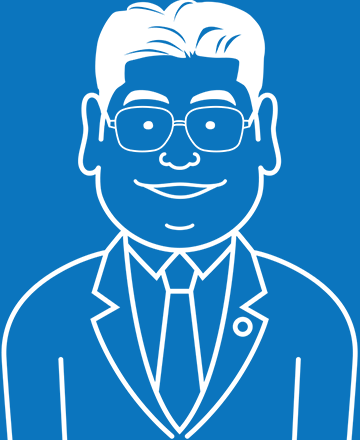【破産】経営者として最後の決断のタイミングは、何を基準に?
コロナ融資の返済も始まり、
ここ下関でも、私が弁護士業務の過程で感じられる肌感覚では、報道される景況感よりさらに実体経済は厳しいようにも感じています。
全国紙でも連日のように、どこかな会社が倒産したと経済欄に掲載されることがあります。
少し前には結婚式場が急に破産して、予約していた挙式ができなくなってしまった、お金も前払いしたのにどうしてくれるんだ、というニュースもありました。
覚えている方も少なくないのではないでしょうか。
取引先・関係者に対して、経営者としての矜持を
これは相当に迷惑がかかってしまいますよね。
何がと言うと、新郎新婦はもちろん、
遠方から呼んでいるお友達、親戚等。
関連する費用として、交通費や宿泊費。
挙式費用の前払金の返還請求権は破産債権にはなりますが、
その他の友人・親戚らが予約したお金は直ちに破産債権にはならないように思われます。
道義上、お呼びした新郎新婦が友人・親戚らにお金を用立てて返すことになるでしょう。
そのお金が損害賠償請求権として破産債権者になるかどうかは、法的にはかなり微妙に思われます。
新郎新婦の精神的・経済的負担は察するに余ります。
だからといって、その新郎新婦を
助ける法律上の手立てはほとんどなさそうです。
(破産債権者として前払金の一部が配当により返済されるかもしれませんが、会社が破産するくらいお金に困っているのですから、ほとんど望み薄でしょう。)
多額の負債を抱えての新婚生活をスタートすることになってしまいます。
その他にも、記憶に新しいのが、
学習塾の倒産がありました。
たしか、共通試験まであと数週間という時点での倒産でした。
受験生が追い込み時期に自習室を使えなくなったり、
冬期講習を受講できなくなる。
なにより荷物の持ち出しや、自習室を探す心理的・時間的負担を考えると、
あまりにも経営者の矜持を疑ってしまいます。
経営破綻させるにしてもタイミングが重要です。
まだ資金繰りが完全に破綻していなかった前年度の年度末には会社を閉じて生徒の新規受入をしてはいけなかったのでしょう。1年かけて別の学習塾に移籍する方法を探るのが社会的責任でしょう。
他方、銀行団と話をつけて社会的影響を考慮して年度末まではなんとかしてつなぎ融資をお願いして引っ張るとか、いろいろ考えはしたのでしょうが、何か方法はなかったのでしょうか。
数年前には旅行会社の破産もありました。
お客様が国外へ出発したあとに破産して、海外に行ったはいいがホテルにも止まれず途方に暮れるというひどい状況があったようです。
こちらも、前払いのお金は破産債権に過ぎませんので、ほぼ返ってこないでしょう。
その他、介護施設の場合も同じです。
入居者の次の行先を手配してから事業停止しないと、入居者はその後どうされるのでしょうか?
食事、介護、医療、いずれも止まってしまえば即、命に関わります。
ご家族が仮にいらっしゃったとしても、すぐにはご家族も自宅介護の対応はできませんよね。
受入先を探すにしても、1日や2日でみつかるものではないでしょう。
もちろん経営環境の悪化で、会社経営を失敗することもあります。経営の失敗そのものは恥じるべきものではありません。
ただ、起業した以上は、最後くらいは、社会的責任として、経営者の矜持として、
できる限り影響の少ないタイミングを見て、
破産の申し立てをしたいところです。
次を見据えるためにも
さらには、適切なタイミングでの破産申し立てというのは、
その後の債権者集会をスムースに行う上でも、
不可欠です。
タイミングを逸してしまうと、債権者に大ダメージを与えて心証を害してしまいます。
債権者集会が大荒れになり、
その後の破産手続きが混乱して長引くことにもなりかねません。
結局は再起を図るうえでも、破産者にとってデメリットです。
また場合によっては破産詐欺のような刑事罰に該当するケースもありえます。
早めに相談に来ていただいたほうが、これらの破産戦略を考えることができる面でも、
それが次の再起や社会的評判にも関わってくるという意味で、
まずは早めのご相談に来ていただきたいものです。
最後の社会的責任を
従業員は未払賃金立替制度があったり、失業保険があったり、公的制度で保護されている部分もあります。
でも、取引先、債権者はありません。倒産防止共済のように自分でガードする仕組みを予め用意しておくことくらいしかできません。
さらには、結婚式のケースのように、関係者(式参列者)を保護する法的制度はほぼありません。
起業した以上は、社会に対して、最後まで責任を取りたいものですね。
当事務所まで、お早めにご相談を。