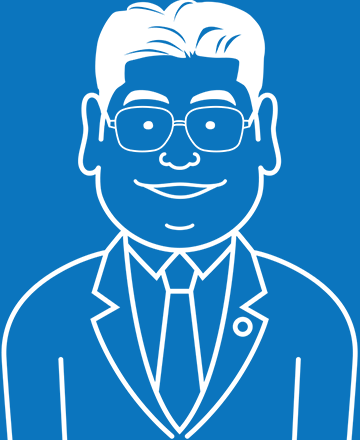認知症の父に母の生命保険が入ってきたら?
ご家族に認知症になった方(例えばここではお父さん)がおられる方からのご相談で多いのが、亡くなられたお母さんの生命保険金が認知症のお父さんの口座に入ってきたというケース。
あるいは、障がいのある子どもに、お父さんの生命保険金が入ってきたというケース。
現預金を相続したりした場合も同様です。
生命保険金ですから、1000万円単位のまとまったお金が入ってくることは少なくありません。
お金が入ってくると、どこから漏れたのかは分かりませんが、鵜の目鷹の目で人が寄ってくるのが常です。
中にはちょっと優しくしてお金をもらえないか、と寄ってくる不心得な人、違法すれすれの訪問販売、文字通りの詐欺師(犯罪者)が寄ってくるかもしれません。
この場合、お父さんやお子さんは、自分で自分の財産を守ることができません。
このような場合に法律が用意しているのが成年後見制度です。
ただ、現在の成年後見制度は、制度の大がかりすぎて使い勝手が悪い側面がないではありません。
本人の日常生活のためにいちいち後見申し立てをして後見人制度の下で、お父さんやお子さんをサポートしていかないといけないというのでは、
経済的負担も大きいものです。
そこで、このようなご家族間の負担から解放しつつ、お父さんの財産を守るために作られた制度の1つに、「後見制度支援信託」というのがあります。
後見制度支援信託とは?
後見制度支援信託とは、被後見人、すなわちこの場合お父さんの財産のなかでも、日常的に支払いをするうえで必要な金銭以外、つまり日常的に使用しないであろう金銭を信託銀行等に信託してもらう制度です。
後見制度支援信託を利用すると、後見人(たとえばご家族)は日常的に支払う分の金銭については、お父さんの代わりに管理することが出来ますが、信託銀行に信託した金銭については、家庭裁判所の許可がないかぎりは払い戻しや口座解約ができなくなります。
では、どのようなメリットがあるでしょう?
被後見人の現預金を保全できる
第1に、一々裁判所の許可が必要になるため、支出の必要性が監督されます。不必要なお金の支払いを事前にストップすることができます。弁護士からすると、出ていったお金を取り返すのは大変ですが、お金が出ていく前であればいろいろな法的構成を考えることができます。
これにより、消費者被害などによる支出にストップがかかり、お父さんの大部分の現預金が守られます。
第2に、日常的な支払い以外の金銭管理からご家族が解放されることにより、ご家族間の争いや精神的負担を減らすことができます。
日常的に支払う金額は決まっているでしょうから、その後、使途不明金が生じにくくなり、ご家族の負担を軽減できるメリットは大きいと思います。
後見人への報酬額を抑えられる
第3に、現在の運用では(地域によって違いますが)、被後見人におおよそ現預金が約1000万円を超える場合は、ご家族が単独で後見人に選任されることは少ないところです。
少し太めの生命保険に入っていれば、死亡保険金が約1000万円を超えることはざらにあります。
成年後見人が選任されれば、基本的には本人が死亡するまでずっと後見人への毎月の報酬が生じることになります。
これに対して、後見制度支援信託を使えば、約1000万円以上の現預金を信託銀行等へ信託することで、(専門職後見人が辞任して)ご家族が後見人を引き継ぐことができるようになります。
これにより、後見人への毎月の報酬額を下げられることになります。
家族のことは家族で決める
実は、この制度の活用によって、外部の専門職をいれずに、家族だけでお金のことを決めていくことができるようになります。(ここではその生命保険金の使い道)
反対に、この制度を使わなければ、裁判所から、後見人として外部の専門職(弁護士等)や後見監督人の選任を要求されることが多いです。これによって、報酬が発生するだけでなく、家族以外の専門職がそのお金の使い道についてチェックをしてくるので、家族とその専門職との間で対立が起きることも少なくありません。
それがこの制度の活用によってなくなるのです。
家族のことは家族で決められるようになる。
これが一番大きなメリットではないかと思います。
認知症の父に、母の生命保険が入ってきたら・・・
残されたお父さんのこの先の介護のためにも。
信託できるものは現預金のみですが、
当事務所としては、家族のことは自分たちで決めたいというご意向がある方に向けては、
後見制度支援信託を想定した成年後見人の選任申立という方法をご案内しながらサポートすることもできます。
まずはご相談にいらしてくださいませ。