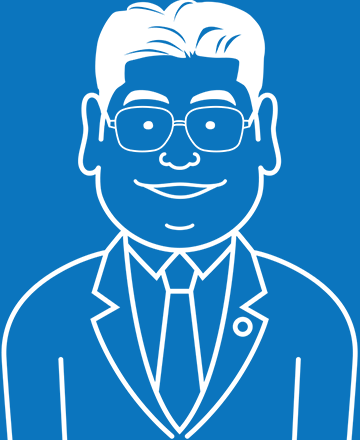老老相続対策として何ができる?
当事務所では相続に関するご相談をお受けすることがよくありますが、
下関という土地柄か、時代の影響か、いくつか特徴があるような気がします。
そのうちの一つは、相続人も被相続人もともに高齢者のケースが多いことがあります。
あるケースでは、100歳の方が亡くなれば、そのお子さんも70代、80代です。相続人の方も後期高齢者という場合も少なくありません。
またあるケースでは、子どもなく亡くなった場合、相続人は兄弟姉妹になります。仮に兄弟姉妹が平均寿命である80代で死亡した場合、その相続人である兄弟姉妹も70代から90代です。
厚生労働省の統計によれば、65歳以上の12.3%が認知症です(2022年度)。
昔の方は兄弟姉妹が多くいらっしゃることが多いので、7人兄弟姉妹がいれば、一人は認知症の相続人がいてもおかしくありません。
進まない相続と守れない生活
相続人の中に、たとえば認知症の方がいらっしゃる場合は、
(事理弁識能力の程度にもよりますが)成年後見人(遺産分割調停の場面に限定した特別代理人という方法もあります)を選任しない限り、相続が進みません。
その申立てや選任、そして遺産分割協議をスタートするまでに、
半年くらいかかることもザラです。
その間、銀行から被相続人のお金をおろして税金を支払ったり、家屋を売却したり、リフォームをしたりすることができなくなります。
つまり、その間、目の前にお金があるのに誰も手が出せない状態になるのです。
せっかく、被相続人の方がご家族を守ろうと財産を遺されたとしても、
その想いが無にされてしまいます。
だからこそ、事前の準備が必要になってくるのです。
生前贈与・家族信託・遺言
ご家族、ご親戚や知人の中に、
これまで相続人をトラブルもなく長らくケアされてきた方がいらっしゃるのであれば、
その方に、その想いとともに財産を託すという方法があります。
1 生前贈与
誰もが最初に思いつく方法です。
ただ、贈与税が発生すること、一度贈与したら後からお金が必要になっても取り返すことができないこと等のデメリットがあります。
2 家族信託
これは難しい制度なので詳細は別の機会に回します。
3 遺言
亡くなった後の財産の行き先については、遺言があります。
相続対策としては「イロハのイ」です。弁護士的にとっても最もオーソドックスな方法です。
相続人が兄弟姉妹の場合には遺留分がないため、どのような内容の遺言であっても、遺留分侵害額請求の対象とならないというメリットがあります。
ただし、法律により遺言できること、遺言の方式等が決められているため、これらの決まりを守らなければ無効になります。
4 生命保険の活用
受取人に指定されていれば、遺産分割協議を経ずに保険金を受取人単独で受け取れるため、対策の一つとなります。
ただ、当然ですが保険金以外の財産には効力は及びません。
こうした対策をしておかないと・・・
このような対策を事前にしておかないと、
遺されたご家族を守れないだけではありません。
仮に高齢の兄弟姉妹が5人いて、そのうちの一人が認知症である場合、その一人のために、目の前に遺産があるのに遺産分割協議が進まず何もできないという事態にもなりかねません。
そうなると、他の相続人の方にも負担がかかってきます。
その認知症の兄弟姉妹の一人のために成年後見人の選任申立をしたり、遺産分割調停を申し立てて裁判所に特別代理人を選任してもらうなど法的手続が必要になります。
法的手続をとることとなれば、時間も費用もかかります。
地域包括支援センターのケアマネ・相談員の方へ
なかなか、普段の生活の中でこれらの情報を集めて、
事前の対策をしておくというのは、
ご家族の中には難しい方も多いのではないでしょうか。
そしてこれらの対策。
将来の相続人の方が認知症になって要介護状態になれば、後見人を選任する必要が出てくるため、時間も費用も必要になってきます。
要介護状態になれば、遺言を作成しても遺言能力の有無が後々に問題となって、かえってトラブルを招きかねません。
事前の対策をするには、要支援の段階の今こそがチャンスなのです。
だからこそ、普段から支援計画を立てられる際に、
この相続対策について情報提供をご家族の方に発信をされてみて下さい。
そのために必要であれば、個別の相談を承ることも可能です。
ご相談は当事務所へ
タイミングを逸しないためにも。
ご相談はお早めに。